目次
- 51.マルティン・ハイデガー
- 52.カール・ヤスパース
- 53.ジャン=ポール・サルトル
- 54.モーリス・メルロ=ポンティ
- 55.マックス・ホルクハイマー
- 56.ユルゲン・ハーバーマス
- 57.ハンナ・アーレント
- 58.エマニュエル・レヴィナス
- 59.フェルディナン・ド・ソシュール
- 60.クロード・レヴィ=ストロース
51.マルティン・ハイデガー
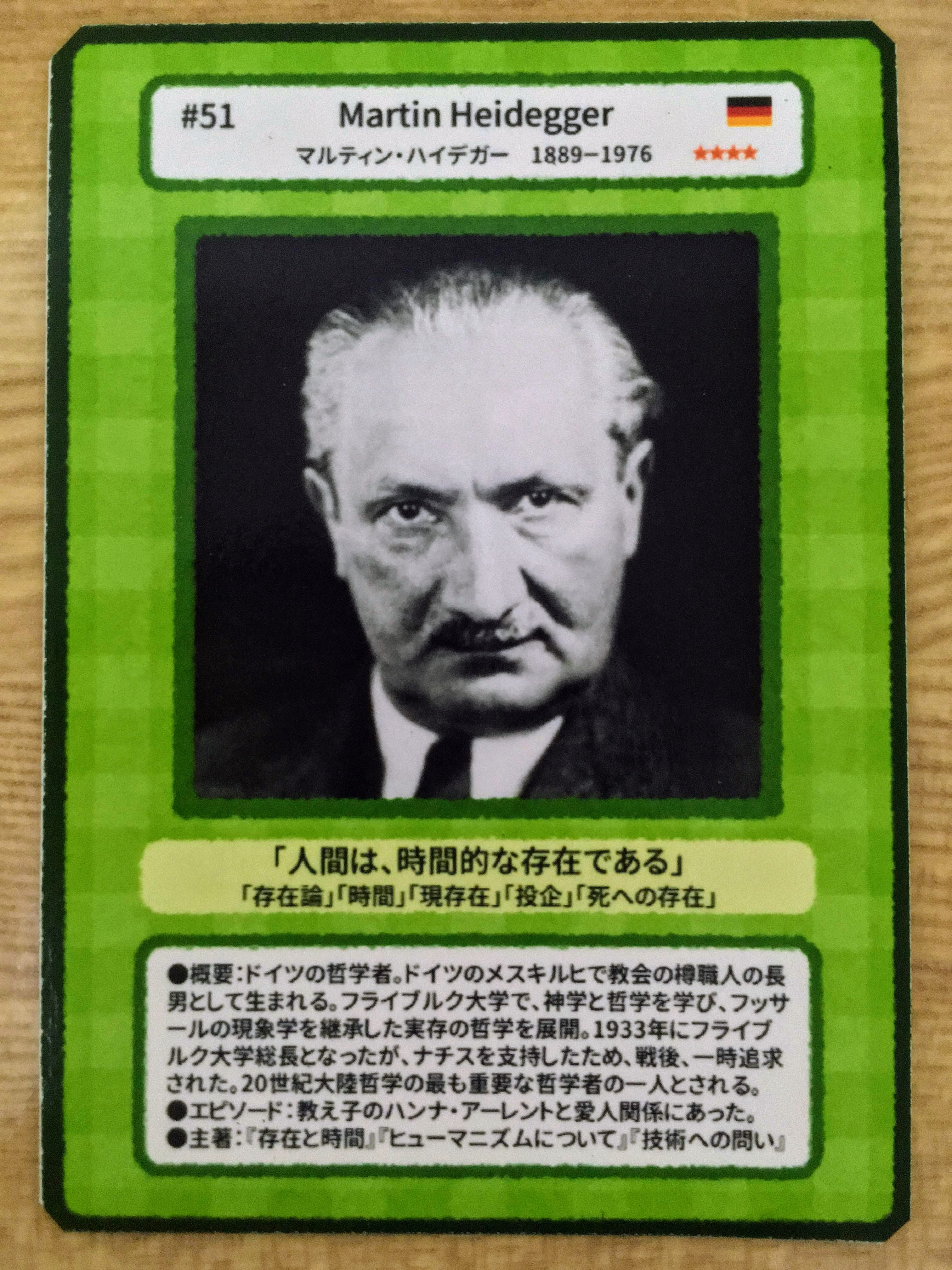
存在論
ハイデガーは、世界を存在者(ザインデス)と存在(ザイン)に分けます。そして、哲学の本来の目的は存在者(ザインデス)について考えることではなく、存在(ザイン)について考えることであると主張しました。
個々の物の性質ではなく、物が存在するとはそもそもどういうことかを考える学問を存在論といいます。存在論はバルメニデスによって古代ギリシアで生まれましたが、認識論が主流になると下火になります。ハイデガーは存在論の復権を宣言しました。
到来/既在
ハイデガーは、未来を到来、過去を既在と呼んで時間を解釈します。到来とは、あるべき自分をめざす可能性であり、既在とは、これまでの自分を引き受けることです。彼にとって時間は私たちの外側を私たちと関係なく流れているものではありませんでした。
現在=到来と既在が出会う実存の現場
現存在(ダー・ザイン)
人間と物や動物の違いは何でしょうか?人間も物も動物も存在者(ザインデス)ですが、自分や物のことを「存在している」と考えることができるのは人間だけです。ハイデガーは、ただ存在しているだけの物に対して、「存在する」という概念を理解できる存在という意味を込めて人間のことを現存在(ダー・ザイン)と呼びました(「ダー」の意味は英語で There is の There。ザインの意味は「存在」。There を意識できる存在という意味で人間のことをダー・ザインと呼ぶ)。
世界-内-存在
ハイデガーによると、何かが「存在する」という概念は人間特有のものです(現存在)。世界はこれらの概念によって作り上げられています。世界とは人間の解釈にほかなりません。そして人間はつねに世界を解釈しながら生きています。このような人間ならではの存在のあり方を世界-内-存在といいます。
世人
ハイデガーは、現存在のあり方を本来性と非本来性の2つに分けます。このうち、非本来性を生きる人間を世人(ダス・マン)と呼びます。世人とはみんなの意見に左右され、みんなと同じような行動をとる人、つまり世間の中に埋没している人のことです。
非本来性・・・世人は日常の出来事に気を奪われ、世間の中に埋没している。みんなと同じ意見を言い、同じ行動をする「誰でもない人」
本来性・・・いつかはやってくる自分の死を自覚している。そしてその日が来るまで、自分らしい生き方をする決意をしている人
被投性(投企)
人は自分から自分の存在を始めることはできません。物心ついた時にはすでに存在しています。このすべての人に共通する状態をハイデガーは被投性と呼びます。やがて人はいつかは死ぬことを自覚し、死までの限られた時間の中、自分の道を進む決意(先駆的決意)をします。先駆的決意によって自分の可能性に自分を投げ入れることを、ハイデガーは投企と呼びます。
実存=死への存在・・・死ぬまでの限られた時間をつねに意識して自分の道を進む 死ぬまでの時間を精一杯生きよう!
死への存在
人間は死から逃れることはできません。そして、人間だけが自分に死が訪れることを知っています。死は恐怖以外の何物でもありませんが、通常私たちは日々の雑用に気を取られ、死の不安から目を背けて暮らしています。
けれども自分の死と真剣に向き合ったとき、人は自分の使命を確信し、それに向かって進む決意をするとハイデガーは言います。
この段階で人は実存の本来性に目覚めます。ハイデガーにとって実存とは自分に残された時間の有限性を自覚している死への存在のことなのです。
ハイデガーはつねに自分の死を念頭に置き、今の自分から死ぬまでを全体と考えました。この考えは、自分の存在自体も全体の一部となってしまう恐れがあります。ハイデガーは一時期ナチスに入党していましたが(1年で脱退)、彼の思考はどこかでナチスの全体主義に通ずるものがあったのかもしれません。
52.カール・ヤスパース

限界状態
人間は物のようにただ存在するのではなく、実存として生きています。ヤスパースは、人が真に実存する(自分らしくなる)瞬間は限界状況に立たされた時だと考えました。限界状況とは死、罪、戦争、偶然の事故など、科学で解明したり、技術で解決したりできない人生の壁をさします。
限界状態で人は自分の有限性を思い知ることになります。
けれども限界状況による真の挫折を経験した時、その悲しみのすべてを包み込む神のような存在である包括者(超越者)に出会います。この出会いで初めて人は真の実存に目覚めるのです。
けれども限界状況は包括者に出会うだけでは乗り越えられません。同じく限界状況の中にいる孤独な他者とお互いに真の自分をぶつけ合う実存的交わり(愛しながらの戦い)が必要だとヤスパースは言います。
ヤスパースは妻がユダヤ人だったため大学教授の職を追われます。その後、強制収容所への送致に対し、2人で自宅に立てこもります。もはや2人で自殺するしかなくなった寸前に戦争が終焉に向かい、助かりました。ヤスパースとその妻も実存的交わりによって限界状況を乗り切ったのです。
53.ジャン=ポール・サルトル

実存は本質に先立つ
サルトルは、実存主義を「実存は本質に先立つ」という言葉で表現しています。ここでいう実存とは人間の存在という意味です。そして本質とは、その物がその物であるためには欠かすことができない条件をいいます。たとえばハサミの本質は「切ることができる」です。この条件がなければハサミに存在理由(レゾンデートル)はありません。物は、先に本質があり、その後で存在します。けれども人間は気がついたら実存しています。したがって後から自分自身で本質を作らなければならないわけです。
実存は本質に先立つ・・・人間は気がついたら実存(存在)している。よって本質を後から自分自身で作らなければならない。つまり人間の実存(存在)は本質に先立つ。サルトルは言う。「人間は初めは何者でもない、人間は後から自分で人間になるのである」
人間は自由の刑に処されている
物には存在理由が先にあるので自由はありません。けれども人間は自分の存在理由を自由に作ることができます。何になろうが何をやろうが、その人の自由なのです。ただし、そこには不安と責任がともない、時に大きな重荷となります。サルトルはこのことを「人間は自由の刑に処されている」と表現します。
メモ:人間の「主体性」を重視するサルトルの思想は、構造主義の台頭とともに、影響力を失っていった
即自存在/対自存在
サルトルにとって私は初めから存在するものではありません。初めから存在するのは意識だけです。その意識が、コップなどの物、過去の自分、他人などと自己自身を区別しながら徐々に私を作り上げていきます。
このように、絶えず自己を意識しながら私という本質を作っていく人間のあり方(実存は本質に先立つ)をサルトルは対自存在と呼びます。反対に、物のように、初めから本質として固定された存在を即自存在と呼びました。
そして対自存在は、過去の自分とはもちろん、今現在の自分とも区別します。私が意識した時はすでに今を乗り越えているからです。自分の可能性をつねに先取りしているという意味で、人間は「あるところ(過去から今まで)のものでなく、あらぬところ(未来)のもの」なのです。ところがこの無限の可能性、すなわち自由は人を不安にさせます。サルトルは、ときに人は、他人から与えられた役割を演じることでこの不安から逃れようとしてしまうと考えました。
アンガージュマン
歴史は理想的な方向へ向かっているとヘーゲルは考えました。そしてマルクスは、資本主義に代わる新しい歴史の登場を予言しました。はたして本当なのでしょうか?サルトルは積極的に社会に参加し、みずからの手でそれらを実現しようと訴えます。社会に参加することは社会に拘束されることですが、その社会を変えるのも自分たちだとサルトルは言います。彼は社会参加のことをアンガージュマンと呼び、みずからそれを実行していきます。サルトルの活動は日本の全共闘運動など、世界中の社会運動に大きな影響を及ぼしました。
晩年、構造主義の台頭により、サルトルの考えは大きな批判にさ らされますが、彼は死の直前まで民族解放の活動を続けます。他者に対して責任を負わず、黙って見ていることは、自由を主張した彼にとって不自由以外の何物でもなかったからなのかもしれません。
メモ:英語では commitment と訳されることが多い
54.モーリス・メルロ=ポンティ

身体図式
自転車に乗っている時、ハンドルを持つ手やペダルをこぐ足は自分が意識しなくても坂道や障害物に勝手に対応します。なぜ、そのようなことが可能かというと、手足などの身体は、意識とは異なる独自の意志を持ち、お互いに連絡をとりあって、行動のための図式を作っているからだとメルロ=ポンティは考えました。この図式を身体図式といいます。
身体図式が無ければパソコンのブラインドタッチや楽器の演奏はもちろん、歩くこともできません。
事故で足を失った人は、存在していないと意識しているはずの足をつい使おうとしてしまいます。それはまだ身体図式の更新ができていないからだと彼は言います。けれどもやがて身体は杖を取り入れた新しい図式を作り、うまく歩けるようになります。
このことから身体図式は自分の身体内だけでなく、杖のような道具や身のまわりの物事との間にも作られていることがわかります。メルロ=ポンティは自分の身体こそが自分と物や世界、さらには自分と他者をつないでいると言います。
〈肉〉
私とは私の意識のことであって、私の身体は私ではなく、周りの世界と同じ客体であると見なすのがデカルト以降の近代哲学の考え方でした(心身二元論)。
けれども意識は、身体の中にあります。意識は決して空を飛んでいるわけではなく、身体がなければ存在できません。このことからメルロ=ポンティは身体は客体であると同時に主体でもある両義的なものだと考えました。
また、私たちがリンゴを見たりリンゴに触れたりするとき、リンゴは私たちに対して客体です。けれどもこの時、リンゴを見る眼(眼は身体の一部)やリンゴに触れる手は客体ではなく主体だと彼は言います。さらに、眼は他者を見ると同時に他者からも見られています。握手する時も、他者の手をにぎっているとも、他者からにぎられているともいえます。
メルロ=ポンティは、身体を「主体として感じるものでもあり、客体として感じられるものでもある」と表現します。身体があるからこそ、私たちは世界に触れることができるし、世界は私たちに触れることができます。私たちの意識は身体を通じて世界とつながっているのです。メルロ=ポンティは身体と世界が接する部分を世界の〈肉〉と呼びました。
55.マックス・ホルクハイマー

道具的理性
フランクフルト学派のメンバーであるホルクハイマーやアドルノはナチスのファシズムやユダヤ人の虐殺に、近代以降続いてきた理性万能主義の限界を見て取ります。
そして、そもそも近代の理性は「自然を支配する目的を成し遂げるための道具」として発展してきたことを指摘します(知は力なり)。
何かの目的を達成するための道具的理性は、利益追求に結びつき、ファシズムの政治政策や戦争兵器開発の道具となってしまっているとフランクフルト学派は考えました。
また、フランクフルト学派の心理学者フロムは、自由を獲得した近代の人々が自由の孤独に耐えかね、みずからナチスの権力に服従してしまう心理を考察します。
さらにフランクフルト学派は、実証のみを重んじる科学万能主義に対しても、現実を部分的に分析するだけで、大きな視点を持たない危険性があると指摘しました。
56.ユルゲン・ハーバーマス

57.ハンナ・アーレント

58.エマニュエル・レヴィナス

イリヤ
ユダヤ人であったレヴィナスの家族、親戚、知人のほとんどがナチスに殺されてしまいました。レヴィナスだけは何とか強制収容所から帰還したものの、すべてを失います。それでもなお世界は何ごともなかったようにそこに存在していました。
すべてを失ったのに、まだ存在している……。一体何が存在しているのでしょうか?レヴィナスはこのような主語無き存在をイリヤと呼んで恐れました。
自分中心の世界を創り上げれば、イリヤの孤独から逃れられるのでしょうか?
答えは否です。自分中心の世界を創ったとしても、イリヤの孤独から抜け出すことはできません。なぜなら結局それは、自分が理解できるものの範囲で世界を構築しているだけだからです。
おそろしいイリヤから抜け出すことは不可能なのでしょうか?レヴィナスは他者の顔にその道を見いだします。
59.フェルディナン・ド・ソシュール

ラング/パロール
ソシュールは、言語をラングとパロールという2つの側面に分けて考察しました。ラングとは、ある言語の規則や文法のことであり、パロールとは個々の発話行為のことです。そして、このラングとパロールをあわせた言語活動全体をランガージュといいます。ソシュールの言語学では、ラングを分析することに重点が置かれました。
シニフィアン/シニフィエ
ソシュールは文字や音声をシニフィアン、それからイメージされるものをシニフィエ、2つをあわせてシーニュ(記号)と呼びます。こう呼びなおすことによって、それまで考えられてきた世界のあり方と異なる、もう1 つの世界のあり方が見えてきます(言語の恣意性)。
言語の恣意性
フランス人は蝶も蛾も「パピヨン」という言葉で言い表します。つまりフランス人にとって「蛾」(あるいは蝶)は存在しません。このことで「蝶」という存在があるから私たちはそれに「蝶」という名前をつけているわけではないということがわかります。このように物と言葉の結びつきに必然性がないことを言語の恣意性といいます。
まず一つ一つの要素が存在していて、それに名前が振り当てられているのではありません。私たちが世界を言語で区切ることで一つ一つの要素が存在できているのです。そして私たちはこの言語世界の範囲内で思考しています。言語は思考を伝達する手段だけでなく、反対に思考を決定する原因にもなっているのです。
目の前のリンゴの実在は単なる思い込みかもしれません。フッサールはエポケーという方法で現象学的還元を行うと、思い込みの根拠をつきとめられると考えました。
60.クロード・レヴィ=ストロース

構造主義
サルトルは、人間は自由であり、主体的に行動することが大切だと考えました。けれどもレヴィ=ストロースは違いました。
なぜなら、レヴィ=ストロースは人間の思考や行動はその根底にある社会的・文化的な構造に支配されていると考えたからです。彼はソシュールの言語学(言語の恣意性)を人間社会に適用して、この考えを導きだしました。
こう考えると人間の主体性は構造に規定されることになります。レヴィ=ストロースは、サルトルの主体性を強調する考えを、西洋独特の人間中心的な考えだと言って批判しました。
文化人類学者であったレヴィ=ストロースは、いくつもの未開社会の人たちと生活をともにし、人間の行動を規定している構造を調査しました。たとえば、ある2つの未開社会同士の間で行われる女性を交換する風習の裏には、近親婚の禁止という人類共通の構造が見て取れると彼は言います。
また、2つの未開社会の人たちはお互いに、女性交換の風習の意味を知りませんでした。行動の意味は、一方だけから眺めてもわかりません。物事はつねに二項対立を軸にして捉えるべきだとレヴィ=ストロースは主張します。現象の意味をそれ自体からでなく、それと関係する社会や文化の構造から読み取ろうとする考え方を構造主義といいます。
野生の思考(↔文明の思考)
サルトルは、主体的に社会に参加して歴史を進歩させようと主張しました(アンガージュマン)。けれどもレヴィ=ストロースはこの考えに強く反対します。
歴史を持たないボロロ族やカリエラ族と生活を共にした文化人類学者のレヴィ=ストロースにとって、サルトルの主張は「人間によって歴史は正しい方向へ向かう」という人間中心的な西洋思想の押し付けに見えたのです。
西洋人が設計図をもとに計画的にものを組み立てるのに対して、未開人はその場のあり合わせの材料を使い回すブリコラージュ(器用仕事)でものを組み立てるとレヴィ=ストロースは言います。ブリコラージュは決して幼稚な発想ではなく、地球環境や社会の安定を維持するためにはきわめて論理的かつ合理的な手段です。レヴィ=ストロースは、彼らの思考を、西洋の文明の思考(科学的思考)に対して野生の思考と呼びました。
文明の思考は今、深刻な環境破壊や核兵器を生み出しています。野生の思考がブリコラージュの発想で文明の進歩(歴史)を無意識に拒むことには意味があるのです。ものごとをどちらか一方からではなく構造的(構造主義)に考えると、野生の思考と文明の思考は互いに補完し合うべきものだということが見えてくるとレヴィ=ストロースは言います。